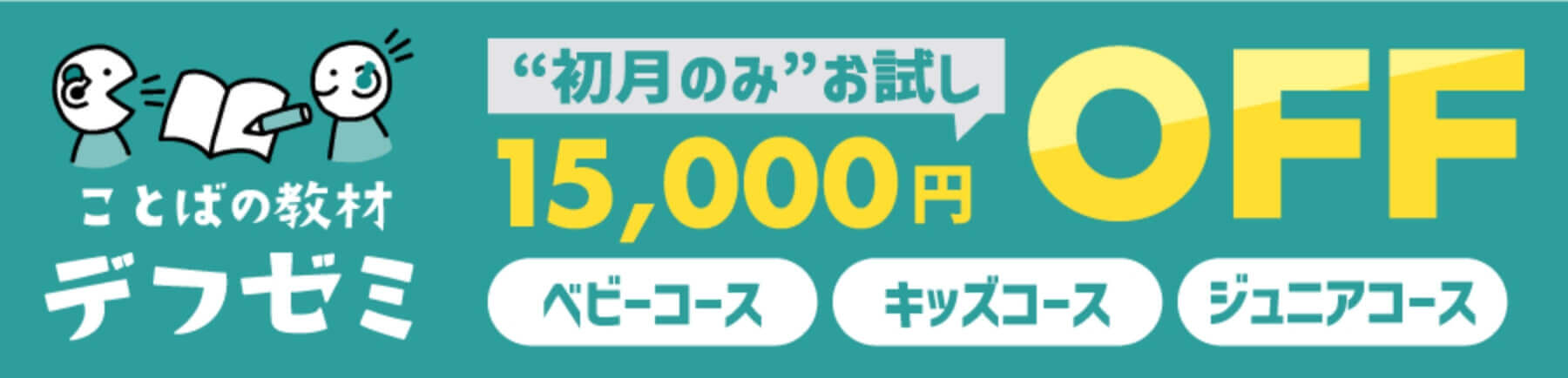アメリカに来てもうすぐ3年。デフサポ、やめてません!最近の私と日米の難聴児教育について
公開日2025/10/31最終更新日2025/11/01
日常
アメリカに来てもうすぐ3年ってホント?!
こんにちは、ユカコです。気づけば 2023年の冬にアメリカに行き始めてもうすぐ3年。だいたい1/3は日本で生活し、2/3がアメリカで生活している感じになります、InstagramやYoutubeは変わらず更新していますが、ブログはなんと4年ぶりの更新でした…!月日が経つのが早すぎる!!!
実は「ユカコさんアメリカ行ってるし、もうデフサポはやってないでしょ?」と聞かれることがあり・・・。それを聞いて焦ってブログを書いているこの頃です。結論から言うと、もちろんですが、デフサポ、やめてません!!ちゃんと続いていますのでご安心ください。
私はポンコツなんですが今までずっと、デフサポは本当に有能な仲間に恵まれていて感謝しかありません。
難聴のユカコ、アメリカでどう過ごしてる?英語での会話は?
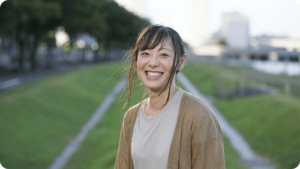 ユカコ
ユカコ一旦私の近況報告を話すと子供はすでに小学校5年、3年になりました。丸2年学校に通ってようやく英語を使うのにストレスを感じなくなってきた頃です。むしろ逆に日本語が停滞してきていて「ことばが大事!」とあんだけ偉そうに皆さんに語りながら、”我が子のことばが中途半端”なことにものすごく危機感を抱いてます。
そして私自身も日本にいたときとはまた少し違った生活を送っています。一番の大きな違いは日本だと何でも一人で行けるしお友達にも気軽に会いに行けるのが当たり前ですが、アメリカだと全て車で送迎っていうところですね。学校も習い事も全て車での送迎が必須です。なので仕事を車の中や外のベンチとかでやることが増えました。そこが意外と大変かもしれません。
そして肝心の聞こえない私の英語はどうなん?と。英語はね、ママ友の英会話が難しすぎてぶっちゃけ全然駄目です。もう開き直って翻訳アプリを使ってます。カフェとかだったら注文できてます!この辺はぜひYoutubeをご覧ください。
さて、今日の本題!アメリカと日本の難聴児の教育の違いについて。
アメリカの難聴児教育は進んでいるのか?
アメリカの支援は実際どう?
これ結論から言うと日本より良い面もあれば、逆に日本の方が良い面も大きくあります、
アメリカでは、生まれたばかりの赤ちゃん全員に「新生児聴覚スクリーニング」が義務づけられています。そこで聞こえに心配があると分かると、すぐに州ごとの「Early Intervention(早期支援プログラム)」につながります。
ここでは0歳から3歳まで、家庭訪問や言語聴覚士(Speech Therapist)によることばの練習、親へのアドバイスなどが行われます。日本でいう「療育」に近いですが、アメリカでは法律(IDEA法)で守られているので、親が「支援を受けさせてください」とお願いすれば、必ず何らかのサポートが用意されます。(一応・・・)
ちなみに、「評価(スクリーニング・発達検査)」部分はほとんどの場合無料になります。ただ、サービスの提供(言語・リハビリ等)は、州や地域によって「無料」または「所得に応じた分担(スライディングスケール)」がある場合があります。
ただ、州によって支援の内容に差があるのが正直なところです。大都市なら専門家も多く病院も近いのですが、地方に行くと「聴覚の専門家がいない」「移動に3−4時間かかる」というのも珍しくありません。そんなときはオンライン(Telehealth)でリハビリを受けることも増えてきました。また、人工内耳などは州によっては民間保険でカバーが義務化されていないことも多く、家庭が負担しなければいけないことも多々あります。
またアメリカは広いので、医療や教育のレベルが地域によってまったく違うんです。専門のオーディオロジストが少ない地域では、予約が数ヶ月先になってしまうこともありますし、医療費の仕組みが日本と大きく違うため、保険に入っていないと治療費が非常に高額になります。
州によってはMedicaid(低所得層向け公的保険)やCHIP(子ども保険)がありますが、申請が複雑で途中で更新し忘れると補助が切れてしまうこともありますし、家庭状況によっては入れないことも・・・。
ただ、公立の学校に入ると、学校にリハビリの先生が来てくれたりするのでそういった意味では日本よりも楽&専門的な療育を週に数回受けれる子どもたちもいます。
またその恩恵を受けることが出来た場合は専門性はとても高い人が多いためそこはかなりいいポイントです。
日本はやっぱり健康保険制度が充実してる!
日本は健康保険が全国どこでも使えて、人工内耳の手術や補聴器関連も自治体による助成制度が整っています。また、補聴器は原則医療保険の対象外ですが、。ただし補装具費支給制度で公費支援があり、原則一割負担、所得に応じた月額上限の仕組みが基本的にあります。
そう考えると、「安心して長く通える医療体制」という面では、日本のほうがずっと安定しています。また、都道府県ごとに最低1校は基本的にあることが多いこと、療育センター、難聴学級や通級なども充実しているため、場合によってはアメリカに比べると日本のほうが対面でのフォローはたくさんある、ともいえます。
やっぱり専門性の高い情報と、親御さんの力は必要!
なので行く前はアメリカのほうが進んでるんだろうな〜って思っていたのですが、意外と制度的にはそうとも限りませんでした。
ただ専門家の専門性に関してはアメリカのほうがスピーチセラピストやオーディオロジストのそれぞれの資格がしっかりあり、専門性が圧倒的に高くなるため、しっかりと療育につながることが出来た場合に伸びる可能性は高いなと感じています。
デフサポは日本で唯一AVTの資格を取っている矢崎先生の協力を得て専門性の高い教材を作成させていただいているので、そこは私達の強みポイントです。
そして、日本もアメリカももちろん場所によってはまだまだ本来得られるべき療育が得られず、「親御さん頼み」になっているところがたくさんあります。
制度を変えていく必要はありますしそのためにも動いていますが、それが変わるまでに難聴児は成長していってしまいます。
なので今難聴児がいるご家庭で大事なことは以下3つだと思っています。
1、情報:親御さんに「質の高い情報やどんな療育をしたらいいか?」を知ってもらうこと。
2、対面:病院・療育機関とも連携して、聴力検査をしたり対面でサポートをしてもらえること。
3,家庭療育:実際に難聴児にいろいろな声掛けをしてもらったり、ことばを豊かにしていくためのサポートを親御さんや身近に関わる大人が難聴児に実施できること。
そのお手伝いとしてデフサポができることとしては、どこに住んでいても、共働きで平日は忙しくても、「質の高い情報やどんな療育をしたらいいか?」を知ってもらうことだと思っています。そこに関しては最大限お手伝いできるかなと思っていますので、困ったことがあればぜひぜひご相談いただければと思います。
デフサポいまはどんなことやってるの?
親御さんに向けた「ことば」の教材
基本的にはこれまでと全く変わりません。補聴開始〜小学校6年生までの教材をカバーしています。難聴児の親御さんに向けて「どういうふうに声掛けをしたらいいか?」のヒントになる教材を送らせていただいています。
また、教材を継続してくださっている方限定でLINEもつながっており、そちらでいつでもどんなことでもご連絡いただいたらそこに対しての疑問や不安点をお答えさせていただいています!また、定期的に言語聴覚士か私とオンラインでのセッションを実施しています。
企業研修・講演・コンサルティング
アメリカに行って引き受けられないと思われがちですが、実は意外と(?)変わらず継続させていただいております。オンラインでしたらいつでも引き受けておりますし、対面で直接講演や研修をさせていただくことも多々あります。特に6月7月あたりは日本に滞在していることが多く、そのあたりでしたら比較的柔軟に対応することが可能です。
例えばテーマとしては以下です。
・難聴児の当事者としての視点から(苦労したこと、学生時代大変だったこと)
・障害者雇用を実施するにあたって(障害者雇用の問題点、整備すべきポイントなど)
・障害者への接し方、差別にならないためには?(接客、対人関係の職種向け)
・ダイバーシティ研修
・当事者・企業人事としての視点から
難聴について認知してもらう活動
こちらもアメリカでも日本でも継続して活動を続けています。アメリカ生活で頑張っている日々もたくさん出しているので、もし存在は知ってるけどまだ面倒くさくて登録していないわ〜って方がいらっしゃったらぜひとも登録をお願いします!(笑)やる気が出ます!
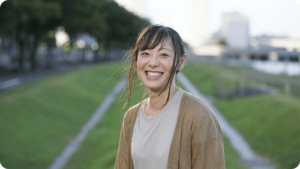 ユカコ
ユカコ個人的な話をすると、本当にたくさんのろう者・難聴者が当たり前にSNSで発信するようになって本当にすごい嬉しいです!もっともっと色んな人がいて当たり前に日常生活を過ごしているんだなあ〜と伝わっていけばよりフラットな世の中になっていくんじゃないかなと楽しみにしています。
というわけで久しぶりのブログでしたが、やはり文字を書くのって大事ですね。そしてアメリカに来てからなおさら「ことば」「母語」の大切さは改めて痛感させられています。習い事や勉強に追われていて、時間のない現代っ子たち。家庭によって何を優先するかはバラバラですが考える力だけはしっかりつけられるようにしていきたいですね。
変わらずデフサポはこれからもやっていきますのでご安心ください。
最後まで読んでくださってありがとうございました!
関連記事
■コミュニケーション
難聴児が習得しづらい言葉6選!フォローが大切!
公開日2015.09.28 更新日2017.12.15
■コミュニケーション
【聴者の私から見た、難聴の友人ユカコについて:後編】~ユカコから学ぶコミュニケーション力~
公開日2020.02.10 更新日2020.02.16
■コミュニケーション
聴覚障害者が運転免許を取得するための5ステップ
公開日2016.01.26 更新日2016.01.26
■コミュニケーション
【ユカコの話】私が関西弁をしゃべれるわけ
公開日2015.09.30 更新日2015.11.27
■コミュニケーション
【ユカコの話】聞こえなくても素敵な人にはなれる!
公開日2015.11.11 更新日2015.11.27
■コミュニケーション
2018年のお礼のご挨拶と私の想い
公開日2018.12.31 更新日2018.12.31
カテゴリ一覧
難聴についてもっと知りたい方へ